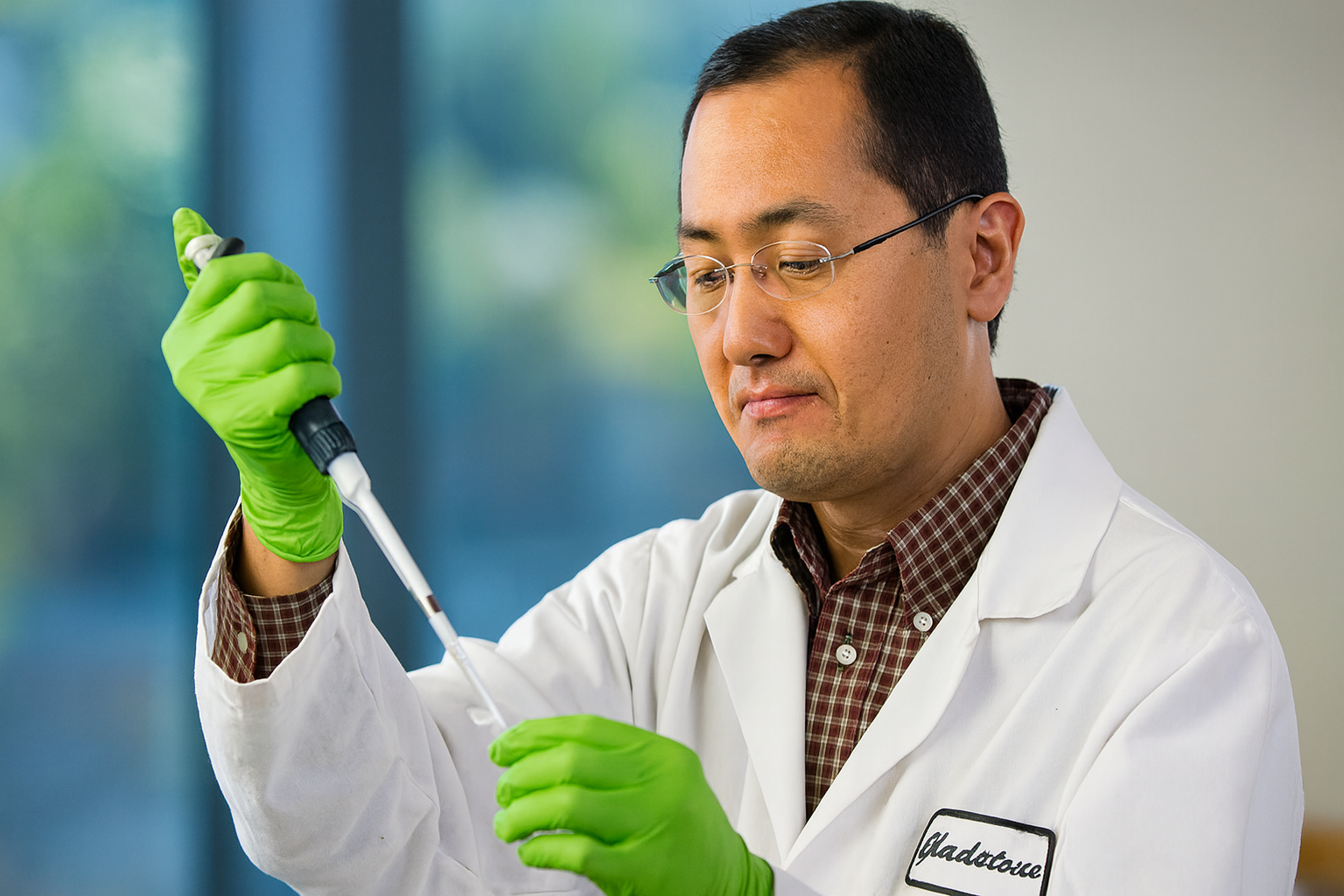- 2006年、山中伸弥は成熟細胞を多能性幹細胞に初期化するOSKM因子(Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc)を発見しました。
- 2016年、Izpisúa Belmonteらは、プロジェリアマウスにおいてOSKMを2~4日間投与し休止するサイクルで部分的なin vivo初期化を示し、寿命が33%延長(18~24週)しました。
- 2020年、健康な中年マウスにOSKMのため2日投与/5日休止のドキシサイクリンサイクルを行ったところ、複数組織で若々しい分子プロファイルと皮膚創傷治癒の促進が見られ、明らかな癌は認められませんでした。
- 2022年、124週齢のマウスにAAV9による誘導性OSKと1日投与/6日休止サイクルを行ったところ、残存寿命が約2倍となり、絶対的な中央値寿命が9~12%延長、残存寿命は約109%増加しました。
- 2023年1月、David Sinclairらは、OSKによるエピゲノム修復で早期老化マウスの老化兆候を逆転させ、腎機能を回復し寿命を延長したことを示しました(Cell誌)。
- 2022年、Wolf Reikのmaturation phase transient reprogramming(MPTR)は、50歳のヒト線維芽細胞の老化マーカーを約30年リセットし、トランスクリプトームやDNAメチル化時計で20歳相当の特徴を示しました。
- 2023年、Life Biosciencesは、OSK療法がNAIONに罹患したマカクザルの視力を回復させ、治療動物は1か月後にほぼ正常な視力を取り戻し、1年以上眼腫瘍は認められなかったと報告しました。
- Turn BioのERA mRNAプラットフォームは、OSKに2つの追加因子を加えて細胞に送達し、主力候補TRN-001は皮膚の若返りを目指し、マウスで毛の再着色も示し、眼・耳疾患で3億ドル規模のHanAll契約も獲得しています。
- Altos Labsは2022年に約30億ドルの資金で設立され、山中伸弥、Izpisúa Belmonte、Jennifer Doudnaらのリーダーを集め、5~10年のスパンで細胞若返りを目指しています。
- この分野全体で安全性や規制上の懸念が続いており、初期化による癌リスクからc-Mycの回避、誘導性システムの利用、全身的なヒト治療の前に長期かつ組織特異的な試験が求められています。
もし老化した細胞に「リセット」ボタンを押して、若返らせることができたらどうでしょう。 老化生物学の最近の画期的な発見により、これはエピゲノムのリプログラミング――DNAを調節する化学的なマーク――を、山中因子として知られる一群の遺伝子を使って行うことで、実現できるかもしれないと示唆されています。研究者たちは、これらの因子を短期間適用することで、細胞のアイデンティティを完全に消し去ることなく、細胞の老化を巻き戻すことができると発見しました [1], [2]。この魅力的な希望は、私たちが加齢による損傷を逆転させ、組織機能を改善し、さらには細胞を若返らせることで老化に伴う疾患を治療できるかもしれない、というものです。本レポートでは、エピゲノムとは何か、加齢とともにどのように変化するのか、山中因子がどのようにして細胞をリプログラムするのか、そして部分的リプログラミングが細胞を幹細胞に変えることなく若返らせる仕組みを解説します。また、最新の研究(2023~2025年)、デビッド・シンクレアやフアン・カルロス・イスピスア・ベルモンテといった第一人者のコメント、Altos Labs、Calico、Retro Biosciencesなどこの科学の実用化を競う主要企業を紹介し、長寿から組織再生までの応用の可能性、そして今後の倫理的・規制上の課題についても考察します。
エピゲノム:その正体と老化の仕組み
あなたの体のすべての細胞は同じDNAを持っていますが、細胞ごとに機能が異なるのは、異なる遺伝子が「オン」または「オフ」になっているからです。エピゲノムとは、DNA配列を変えることなく遺伝子の働きを制御する、DNAやその関連タンパク質上の化学的修飾の集まりのことです [3]。これらの修飾には、DNAメチル化(DNA塩基への化学タグ付け)、DNAが巻き付くヒストンタンパク質の修飾、その他の要素が含まれ、これらが組み合わさって、ある細胞でどの遺伝子がいつ活性化されるかを決定します [4]。本質的に、エピゲノムは細胞がニューロン、皮膚細胞、筋肉細胞などとして振る舞うかどうかを指示する「オペレーティングシステム」のようなもので、遺伝子発現を制御しています。
年齢を重ねるにつれて、エピゲノムは静的なままではなく、特徴的な方法で変化します。特定のエピジェネティックマークは時間とともに蓄積したり消失したりし、若い頃に見られる厳密な制御が失われていきます [5]。例えば、メチル基(化学的なタグ)は、年月が経つにつれて一部の遺伝子領域に蓄積し、他の領域からは消失する傾向があります [6]。これらの変化は高齢の細胞における遺伝子発現を変化させることがあり、多くの場合有害な影響を及ぼします。ある研究者は、「加齢の過程でマークが追加されたり、除去されたり、修飾されたりする……エピゲノムが年齢とともに変化しているのは明らかだ」 [7]と述べています。言い換えれば、80歳の人の細胞は20歳のときとは異なるエピジェネティック情報のパターンを持っています。科学者たちは現在、「エピジェネティッククロック」と呼ばれる、DNAメチル化パターンを読み取るアルゴリズムを用いて、細胞や組織の生物学的年齢を測定しています。これらのパターンは、実際の年齢や健康状態と強く相関しているからです [8]。エピゲノムが年齢とともに予測可能に変化するという事実は、それが単なる受動的なマーカーではなく、加齢の推進因子である可能性を示唆しています。実際、ハーバード大学による画期的な2023年の研究では、エピゲノムを乱すとマウスの老化が加速し、エピゲノムを回復させると老化の兆候が逆転することが示されました [9]。これは、エピジェネティックな変化が加齢の主要な特徴であるという考え、そして重要なことに、それらが可逆的である可能性があるという考えを支持しています。
ヤマナカファクター:細胞を若返らせるリプログラミング
もしエピゲノムが私たちの細胞のソフトウェアであるなら、それを書き換えて時計の針を戻すことはできるのでしょうか?2006年、日本の科学者山中伸弥は、まさにそれを実現するレシピを発見しました。山中は、たった4つの遺伝子—Oct4、Sox2、Klf4、そしてc-Myc(まとめてOSKM、または山中因子と呼ばれる)—を成熟細胞に導入することで、それを多能性幹細胞に初期化できることを発見しました。これは胚性幹細胞に似た状態です [10]。この発見は幹細胞生物学における革命的なブレークスルーであり、山中に2012年ノーベル賞をもたらしました。こうして得られた細胞は人工多能性幹細胞(iPS細胞)と呼ばれ、発生時計がリセットされています:それらは盛んに分裂し、体内のほぼすべての細胞型に分化でき、実質的に細胞のアイデンティティと年齢の両方を消し去る [11] [12]。
山中因子による初期化は、細胞の専門化や加齢に関連するエピジェネティックなマークを消去することで機能します。マックス・プランク研究所のアレクサンダー・マイスナーは、iPS細胞への初期化は「エピジェネティックなマークを書き換えることに尽きる」と説明しています。つまり、加齢とともに蓄積するDNAメチル化やヒストン修飾のパターンを除去し、細胞を「ベースラインの“完璧な”エピゲノム」にリセットするのです [13]。実際には、科学者たちはOSKMを成体細胞(例えば皮膚細胞)に一定期間(通常は2~3週間、培養皿の中で)誘導し、多能性状態に到達させます [14]。この過程で、細胞の外観や挙動は若返ります。例えば、老化した細胞はテロメア(染色体末端の保護構造)が長くなり、遺伝子発現プロファイルがリセットされ、より活発な代謝や修復機能を示します [15]。本質的に、細胞は自分がかつて老いた皮膚細胞だったことを忘れ、再び胚性細胞だと思い込むのです。
問題点: iPSCはもはや機能的な皮膚細胞(あるいは心臓細胞やニューロン)ではなく、白紙の状態です。これを動物の体内で行うと、完全に初期化された細胞は「アイデンティティ」を持たず、本来の組織での役割を果たせません。さらに悪いことに、多能性細胞は体内に導入されると奇形腫(さまざまな組織が混在した塊)を形成することがあります [16]。マウスを使った実験では、ヤマナカ因子4つすべてを体全体で継続的に発現させると、臓器不全やがん性増殖などの致命的な問題が発生します [17]。したがって、完全な初期化はシャーレ内で幹細胞を作るには有用ですが、生体内で広く応用するには危険すぎます。誰も自分の臓器が脱分化して胚様組織になることは望みません。マイスナー博士が率直に述べたように、「これらの多能性因子を治療として個人に誘導するのは良い考えだとは思いません」 [18]。最大の課題は、細胞のアイデンティティを消去せずに初期化による若返り効果を得る方法を見つけることでした。
部分的初期化: アイデンティティを失わずに若返り
ここで部分的初期化という概念が登場します。科学者たちは、もしかするとヤマナカ因子を短期間だけオンにすることで、老化のいくつかの側面を巻き戻しつつ、細胞が専門的なアイデンティティを失ったり腫瘍を形成し始めたりしないようにできるのではないかと考えました。つまり、多能性への道を途中まで進み、そこで止めるということです。「いわゆる部分的初期化とは、ヤマナカ因子を細胞に十分な期間適用して細胞老化を巻き戻し組織を修復するが、多能性には戻さないことです」と、Scientific Americanは説明しています [19]。狙いは、細胞の機能を若返らせること――つまり、古い細胞を若いように振る舞わせつつ、それがたとえば皮膚細胞や神経細胞のままであることです。
このアイデアは、2016年にサルク研究所のDr. Juan Carlos Izpisúa Belmonteらによって劇的な概念実証として検証されました。彼らは、体内でOSKMを間欠的にオンにできるよう遺伝子操作されたマウスを使用しました。このマウスは早老症(プロジェリア)という早期老化疾患を持ち、通常は数週間で死亡します。研究者たちは、マウスにドキシサイクリンという薬を周期的に投与し(ヤマナカ因子を一度に2~4日間だけ活性化し、その後休止期間を設ける)、「部分的」なin vivoリプログラミングを達成しました。結果は驚くべきもので、治療を受けたプロジェリアマウスは有意に長生きし、平均18週から24週と寿命が33%延長しました [20]。また、未治療のマウスと比べて臓器機能も若々しい状態を示しました。注目すべきは、チームがプロジェリア遺伝子変異自体は全く修正しなかったことです。細胞内のエピジェネティックマークをリセットしただけでした。「私たちはエピゲノムを変化させることで老化を変えました。これは老化が可塑的なプロセスであることを示唆しています」とBelmonteは述べています [21]。つまり、急速に老化する運命にあった動物でさえ、細胞のエピジェネティックな風景を若返らせるだけで改善できるということです。図:2016年の画期的な実験で、Belmonteのチームはプロジェリア(早期老化)マウスにヤマナカ因子の発現を短期間誘導しました。治療を受けたマウス(右、毛色が濃い)は、未治療のプロジェリア同腹仔(左、毛色が灰色)よりも長生きし、健康的に見えました。この部分的リプログラミングは、がんを引き起こすことなく老化の兆候を減少させました [22]。
重要なのは、これら部分的にリプログラムされたマウスは、テラトーマを発症したりリプログラミングで死亡したりしなかったことです。これは、OSKMを継続的に発現させた従来の試みでは致命的だったのとは対照的です [23]。因子発現の期間を制限することで、細胞は完全にアイデンティティを失うことはありませんでした――皮膚細胞は皮膚細胞のままですが、より「若い」状態で機能しました。Belmonteの研究は、生体内で細胞の若返りが可能であることを直接示した初めての証拠でした。ある論評では「これは生体動物で細胞リプログラミングが寿命を延ばした初めての報告である」と述べられています [24]。これは、多くの加齢関連の細胞問題(DNA損傷、遺伝子発現異常など)がエピジェネティックな若返りによって改善できることを示唆しています。Belmonteのマウスでは、組織の再生能力が向上した兆候が見られました。例えば、部分的にリプログラムされた高齢マウスは、未治療マウスよりも筋肉損傷や膵臓損傷の治癒が良好でした [25]。
その先駆的な研究に続き、世界中の研究室がさまざまな環境で部分的な初期化を探求してきました。細胞培養では、老齢動物やヒトの細胞を一時的に山中因子に曝露することで、複数の細胞老化マーカーを逆転させることが示されています。例えば、スタンフォード大学のVittorio Sebastiano率いるチームは、修飾mRNAを用いてOSKM(さらに2つの因子NANOGとLIN28を加える)を導入することで、高齢のヒトドナー由来の細胞を多くの細胞型にわたって若返らせることに成功しました。80代や90代の人々の皮膚細胞、血管細胞、軟骨細胞で、より若々しい遺伝子活動パターンや修復機能が回復しました [26]。「私たちはこれを、ほぼ20種類の異なるヒト細胞型で確認しています」とSebastianoは述べています [27]。同様に、2019年にエディンバラの研究者たちは、中年の細胞で一時的にOSKMを発現させることで、細胞がエピジェネティッククロック(DNAメチル化年齢)をポイント・オブ・ノーリターンに到達する前に巻き戻すことができ、細胞が本来のアイデンティティを保持したままエピジェネティックな指標で若返ることを示しました [28]。これらの細胞実験は、部分的な初期化が老化の分子的特徴を「リセット」できることを裏付けています。
若返り効果は、培養皿の中の細胞に限られません。生体内(生きた動物)でも、部分的な初期化は通常の老化(プロジェリアでない)マウスで試されています。その結果は有望ですが、いくつか注意点もあります。2020年、研究者たちは健康な中年マウスで(同じく2日投与・5日休薬のドキシサイクリン周期を用いて)周期的にOSKMを誘導すると、多くの組織がより若々しい分子プロファイルに戻ることを示しました。肝臓、筋肉、腎臓などが、若いマウスに近い遺伝子発現や代謝の特徴を示しました [29]。処置を受けたマウスは再生能力も向上し、例えば高齢マウスが皮膚の傷をより早く治す能力を取り戻しました [30]。重要なのは、OSKMを何度も誘導しても、マウスにがんの発生率の上昇や明らかな細胞アイデンティティの混乱は見られなかったことです [31]。これは、慎重に管理すれば比較的安全にこの処置が行える可能性を示唆しています。
おそらく最も注目すべきは、2022年の研究で、非常に高齢のマウス(124週齢、人間の80代に相当)に対し、遺伝子組み換えマウスではなく遺伝子治療アプローチによる部分的なリプログラミングを施したことです。誘導性OSK遺伝子(がんリスクを減らすためc-Mycを除外)を運ぶウイルスが注射され、マウスにはドキシサイクリンが周期的に(1日投与、6日休薬)与えられました。その結果:治療を受けた高齢マウスは有意に長生きし、コントロール群と比べて残存寿命がほぼ2倍になりました [32]。中央値での寿命延長は約9%~12%の絶対的な増加で、治療開始時点の非常に高齢のマウスにとっては残存寿命が109%増加したことになります [33]。治療を受けたマウスはまた、未治療の仲間よりも良好なフレイルティ・インデックス(健康寿命の指標)を維持しました [34]。この刺激的な結果はまだ1つの研究に過ぎませんが(そしてこのような劇的な寿命延長は今後の検証と理解が必要ですが)、人生の後半であってもエピジェネティックなリプログラミングが測定可能な若返りと健康上の利益をもたらす原理を示しています。科学者たちは、この遺伝子治療による部分的リプログラミングは「哺乳類の健康寿命と寿命の両方に有益である可能性がある」と記しています [35]。
部分的なリプログラミングは、特定の組織や疾患モデルでも有望であることが示されています。注目すべき例は視覚の分野にあります。2020年、ハーバード大学のDavid Sinclair率いるチームは、ウイルスを使ってヤマナカ因子のうち3つ(c-Mycを除くOSK)だけを、視力を失った老齢マウスに導入しました。これらのマウスの目でOSKを継続的に発現させることで、視神経損傷や緑内障の複数のモデルで視力が回復しました [36]。治療を受けた高齢マウスは、若いマウスとほぼ同等にパターンや細部を見る能力を取り戻しました。そして安心できることに、網膜細胞でOSKを1年以上発現させ続けても、腫瘍は形成されませんでした(目の中で) [37]。著者らは、ニューロンは分裂しない細胞であるため、継続的な部分的リプログラミングを特にうまく耐えられる可能性があり、神経系が初期治療の良いターゲットになると示唆しました [38]。別の研究では、心臓発作を起こしたマウスの心臓に6日間だけOSKM遺伝子治療を行いました。その短い6日間で、損傷した心臓は再生の兆候を示し、瘢痕の大きさが減少し、心機能も対照群と比べて改善しました [39]。(注目すべきことに、心臓で12日間のOSKM治療を試みたところ、マウスにとって致命的となりました [40]。これは、タイミングが重要であり、組織によっては過剰なリプログラミングに非常に敏感であることを強調しています。この場合、c-Mycは強力な癌遺伝子であるため、致死的な結果に寄与した可能性があります [41]。)これらすべての発見は一貫した状況を示しています:部分的なエピジェネティックなリプログラミングは細胞や組織を若返らせることができ、より若々しい機能を回復させ、さらには動物において健康と生存率を改善することさえあります。ただし、それが制御された方法で行われる限りにおいてです。2023年のNatureレビューがまとめたように、部分的なリプログラミングはマウスにおいて老化の複数の特徴を逆転させることが報告されています――筋肉の修復の改善、炎症シグナルの減少、代謝プロファイルの向上、エピジェネティックな老化時計のリセットなど――完全な脱分化を伴わずに [42]。要するに、私たちは生物学的な時計を途中まで巻き戻すことができ、細胞は再び若く振る舞う方法を思い出すのです。
最近のブレークスルー(2023~2025年):年齢逆転の最前線を切り拓く
過去2年間で、このエピジェネティックな若返り分野では急速な進展と注目度の高い成果が見られました。研究者たちは重要な疑問に答え始め、さらには臨床応用に向けて動き出しています。ここでは、最新の研究や発見のいくつかを紹介します:
- エピゲノムの回復がマウスの老化を逆転させる(2023年): 2023年1月、デビッド・シンクレア博士とその同僚は、エピジェネティックな変化が老化を引き起こすこと、そしてエピゲノムを回復させることで老化を逆転できるというこれまでで最も強力な証拠を示す画期的な研究を発表しました [43]。13年以上にわたる研究で、チームはDNAの切断を誘導してエピジェネティックなパターンをかく乱し、若いマウスを生物学的に老化したように見せる(白髪、虚弱、臓器機能障害を伴う)マウスモデルを開発しました。その後、これらの早期老化マウスにOSK因子を投与すると、マウスはより若々しい状態に回復し、腎臓や組織の機能を取り戻し、さらに未治療のマウスよりも長生きしました [44]。シンクレアの研究はCell誌に発表され、正常な動物の老化がエピジェネティックな制御によって「意のままに前進・後退させられる」ことの概念実証として称賛されました [45]。「私たちはこの結果が転換点として受け止められることを望んでいます」とシンクレアは述べ、「複雑な動物の生物学的年齢を正確に制御できること、意のままに前進・後退させられることを示した初めての研究です」と語りました [46]。このような発言は大胆ですが、データは説得力がありました。例えば、治療を受けたマウスの臓器やDNAメチル化年齢は、はるかに若い動物に似ていました。シンクレアの研究室や他のグループは現在、このアプローチをより大型の動物で試験しており、非ヒト霊長類での研究も進行中です。エピゲノムのリセットが同様に若返りをもたらすかどうかを調べています [47]。
- ヒト細胞を30年若返らせる(2022年): 英国のDr. Wolf Reik率いるチームは、ヒト細胞の「個性」を失わせずに年齢を巻き戻す新しい手法、maturation phase transient reprogramming(MPTR)を報告しました。彼らは中年の成人皮膚細胞(線維芽細胞)に山中因子を短時間だけ作用させ、リプログラミングの中間「成熟」段階に到達した時点で停止させました。その結果、細胞は幹細胞にはならず、多くの老化マーカーが約30年分逆転しました [48]。処理された50歳の線維芽細胞は、遺伝子発現(「トランスクリプトーム」)やエピジェネティックなDNAメチル化パターンが、複数の「老化時計」指標によると約30年若いプロファイルにリセットされ、20歳のように振る舞いました [49]。機能的にも、これらの細胞はより若々しいコラーゲンを産生し、創傷治癒アッセイでより速く移動し始めました [50]。この若返りの規模は、従来の部分的リプログラミングの試みをはるかに上回るものでした。この研究はeLifeで発表され、若返りと完全なリプログラミングを分離できること、つまり細胞の個性を失うことなく若返りを実現できることを示しました [51]。このような制御されたリプログラミング手法は、安全な治療法開発の青写真となり、細胞のエピゲノムをリフレッシュしすぎないように最適なタイムウィンドウを特定するのに役立ちます [52]。
- 部分的リプログラミングが高齢マウスの寿命を2倍に(2022年): 先述の通り、2022年後半の研究で、非常に高齢のマウスに誘導性OSK遺伝子治療を施した結果、前例のない寿命延長が得られました。Natureの2024年の展望によると、この実験では治療を受けた124週齢のマウス(人間の80~90歳に相当)で残り寿命が109%増加したことが示されました [53]。この治療はマウスの全体的な虚弱度や臓器の健康状態も改善しました [54]。この研究は小規模で再現性の確認が必要ですが、人生の後半に治療を開始しても健康寿命と寿命を大幅に延ばせる可能性を示唆したため、大きな話題となりました [55]。特筆すべきは、がんリスクを減らすためにc-Mycを省略し、AAV9ウイルスベクターを用いてOSK遺伝子を多くの組織に送達した点です [56]。これは実現可能な治療法への一歩であり、トランスジェニック動物に頼らず、他の疾患で人間にも使われている遺伝子治療アプローチを用いている点が特徴です。
- サルの目における視力回復(2023年): 部分的なリプログラミングの非ヒト霊長類での最初の機能的実証の一つが2023年に行われました。シンクレアが共同設立したボストン拠点のバイオテクノロジー企業Life Biosciencesの科学者たちは、OSK遺伝子治療によって加齢性の目の病気を持つサルの視力が回復したと発表しました [57]。この研究では、チームはNAION(50歳以上の人によく見られる視神経損傷)という目の状態をマカクザルに誘発しました。その後、OSK遺伝子を運ぶウイルスベクターを目に注射し、ドキシサイクリンで定期的に活性化しました。次の1か月間で、治療を受けたサルはほぼ正常な視覚反応を取り戻しましたが、未治療のサルは盲目のままでした [58]。これは以前のマウス研究を基にしています。シンクレアのグループはNature(2020年)で、OSK遺伝子治療がマウスの緑内障や視神経損傷を逆転させることを示していました [59]。霊長類でのデータは大きな前進であり、このアプローチが私たちと非常によく似た目でも機能する可能性を示唆しています。共同研究者であるハーバード大学のブルース・クサンダー博士は、視力喪失のような加齢性疾患に対して「新しいアプローチが必要であり、これは非常に有望だと思う」と述べています。 [60] Life Biosciencesは、主力候補であるOSK遺伝子治療(ER-100と呼ばれる)が視神経再生を改善し、緑内障のマウスの視力を回復させ、自然老化したマウスの視力も大幅に改善したと報告しています [61]。現在、サルの目で安全性と有効性の証拠が得られたことで [62]、同社は網膜疾患のヒト臨床試験の準備を進めています。これは、エピジェネティック・リプログラミングの初の臨床的に証明された応用例となり得ます――今日治療法のない視力喪失の一形態に対処するものです。
- OSKMの化学的代替法(2023年): すべての人が遺伝子治療だけに注目しているわけではなく、一部の科学者は遺伝子改変なしで細胞を若返らせる薬剤のような介入法を模索しています。2023年末、研究者たちは細胞で「化学的リプログラミング」カクテルの成功を報告しました。特定の低分子化合物の組み合わせ(しばしば7C、7つの化合物の意)を用いることで、細胞を薬理学的に部分的にリプログラムすることに成功しました――遺伝子は追加していません。ある実験では、老化したマウスの線維芽細胞に7C化学混合物を処理することで、複数の老化指標がリセットされました:細胞の代謝産生、エピジェネティッククロックの値、酸化ストレスレベルがいずれも若い細胞に近づきました [63]。このアプローチは、理論的には錠剤や注射で多くの細胞に到達でき、遺伝子治療よりも制御しやすい可能性があるため魅力的です。初期の結果では、単純な生物で寿命延長も示されています(ある研究では、化学的リプログラミング処理でC. elegans線虫の寿命が40%延長しました) [64]。化学物質だけで部分的なリプログラミングを達成するのははるかに困難ですが(OSKMは遺伝子ネットワーク全体のリセットを引き起こすため)、これらの概念実証は、従来型の薬剤によるエピジェネティックな若返りへの道を開き、安全性の問題を回避できる可能性もあります。たとえば、化学的リプログラミングは薬剤のクリアランスによって簡単に中止でき、OSKM遺伝子が誘発する細胞分裂経路の強い活性化を回避できるかもしれません [65]。この分野の研究はまだ初期段階ですが、非常に有望な別の道を示しています。
これらの進展から、1つのテーマが明らかです。エピジェネティックなリプログラミングは、生物学的な好奇心から潜在的な治療法へと移行しつつあります。シンクレアやベルモンテの研究が示唆するように、老化は私たちがかつて考えていたよりもはるかに可逆的である可能性があります――細胞は遺伝子発現状態の「若々しい記憶」を保持しており、それを再び呼び覚ますことができるのです [66]。しかし、この分野では精密さが重要であることも学ばれています。タイミング、投与量、組み合わせを細かく調整する必要があり、安全に若返りを実現しなければなりません。リプログラミングが不十分だと老化の痕跡は消えませんし、やりすぎると細胞が本来のアイデンティティを失ったり、がん化したりする可能性があります。現在進行中の研究では、安全な若返りプロトコルの特定――例えば、効果が得られる最短のOSK曝露時間の発見や、既知の癌遺伝子を避けるより安全な因子の組み合わせの特定――に焦点が当てられています。中には、まったく新しい「若返り因子」を探している研究者もいます。イギリスのスタートアップShift Bioscienceは、機械学習を用いて多能性を誘導せずに細胞年齢を逆転させる遺伝子セットを探索し、OSKMよりも安全なカクテルの発見を目指しています [67]。
最前線からの声:専門家の見解
エピジェネティックな若返りへの期待は、生物学分野のトップ人材を引きつけ、長寿研究分野を(文字通りではなく)再活性化させています。しかし、それには専門家による健全な懐疑と慎重さも伴っています。以下は、この分野のリーダーたちの見解や引用です。
- デビッド・シンクレア(ハーバード医科大学) – シンクレアは、老化はエピジェネティックな「ノイズ」によって引き起こされ、可逆的であるという考えの著名な提唱者となっています。彼のこの主張を裏付ける最近の実験は大きな話題となりました。「私たちの研究は、哺乳類においてエピジェネティックな変化が老化の主な要因であることを示した初めてのものだと考えています」と、マウスでの年齢逆転を実証した2023年に彼は述べました [68]。マウスの老化をオン・オフできる能力について語る中で、シンクレアは次のように述べました:「これは、複雑な動物の生物学的年齢を正確に制御できること、そしてそれを意のままに前進・後退させられることを示した初めての研究です。」 [69] このような制御は10年前にはほとんど考えられなかったことであり、彼の研究室の「老化の情報理論」―若い遺伝情報は古い細胞にも保存されており、エピゲノムをリセットすることで再び読み取ることができるという考え―を強調しています [70]。シンクレアは、将来的には人間が生物学的に若くいるために、年齢リセット遺伝子治療や薬を断続的に服用するかもしれないとさえ推測していますが、まずは厳格な臨床試験が必要であると強調しています。
- フアン・カルロス・イスピスア・ベルモンテ(アルトス・ラボ、元ソーク研究所) – ベルモンテは2016年のマウスにおける部分的リプログラミング研究の先駆者でした。彼の見解は、老化は決して固定された運命ではなく、修正可能なものであるというものです。「私たちはエピゲノムを変えることで老化を変化させました。これは老化が可塑的なプロセスであることを示唆しています」とベルモンテは述べ、遺伝子の修正なしにエピジェネティックな手段で寿命を延ばせることを強調しました [71]。彼は部分的リプログラミングを、通常は初期胚発生でしか見られない細胞の潜在的な再生能力を引き出すものと表現しています。現在は細胞若返りに特化した新しい研究機関であるアルトス・ラボの科学創設者として、ベルモンテは短期間のリプログラミングが組織の加齢関連損傷を改善する方法を引き続き探求しています。将来的には、私たち自身の細胞を定期的に制御された方法でリプログラミングすることで老化そのものを治療できるかもしれない―つまりエピゲノムの「若さ」を保つためのメンテナンスを行うようなものだ―と彼は示唆しています。同時に、どのエピジェネティックなマークを変えるべきかを理解することが重要だと警告しています。「どのマークが変化し、老化プロセスを駆動しているのかを探る必要があります」と彼は述べ、すべてのエピジェネティックな変化が同等ではなく、老化においてより因果的なものもあるかもしれないことを示しています [72]。
- 山中伸弥(CiRA京都&Altos Labs) – OSKM因子の発見者も若返り競争に参戦しています。彼は日本のAltos Labsで研究プログラムを率いています。山中氏は、部分的なリプログラミングが、完全なリプログラミングよりも先に医療用途を見出す可能性について楽観的な見方を示しています。結局のところ、彼の有名な4因子は細胞のアイデンティティと年齢の両方を消去するため、これら2つの効果を分離することが重要だと認めています。「私たちの[Altosでの]使命は、[この問い]から生まれています。リプログラミングを利用して幹細胞を作るのではなく、既存の細胞に健康を回復させることができるのか?」とAltosの立ち上げに際して述べています [73]。山中氏はタイムラインについて慎重ですが、この分野を再生医療の自然な次のステップと見なしています。つまり、幹細胞由来の移植で古い細胞を置き換えるのではなく、体内にすでにある細胞を若返らせる方向へ進むということです。
- コンラッド・ホッヘドリンガー(ハーバード幹細胞研究所) – 幹細胞の専門家であるホッヘドリンガー氏は慎重さを促しています。最初のリプログラミング若返り論文の「驚くべき観察結果」に感銘を受けつつも、部分的にリプログラムされた細胞がいつ多能性へのポイント・オブ・ノーリターンを越えるのか、まだ誰も正確には分かっていないと指摘しています [74]。彼の経験では、細胞はOSKM曝露2~3日でiPSCになることもあれば、もっと時間がかかることもあり、ばらつきがあります。この不確実性は根本的な安全性の懸念であり、「一つの細胞がiPSCになれば、その一つの細胞だけで腫瘍を作るのに十分だ」と述べています [75]。また、多くの人が行っているようにc-Mycを除外しても、がんリスクがなくなるとは限らないと指摘しています。なぜなら、Oct4とSox2(他の山中因子の2つ)もがんとの関連があるからです [76]。彼の見解では、部分的リプログラミングは魅力的な研究ツールですが、全身治療として「十分にリスクを下げるのは非常に難しい」と述べています [77]。つまり、成人のすべての細胞を安全に若返らせ、どれも暴走しないようにする方法はまだ明らかではありません。そのため、多くの初期応用は、投与を局所化でき、悪影響が限定される特定の臓器(眼、皮膚)に焦点を当てています。
- ジェイコブ・キンメル(カリコ&ニューリミット) – キンメルは、カリコ(Googleの寿命延長R&D企業)および現在はニューリミット(新しいスタートアップ)でリプログラミングに取り組んできました。彼はこの科学に熱心ですが、短期的な利用については現実的です。「私たちがこの分野に投資しているのは、多様な細胞タイプで若々しい機能を回復できる数少ない介入法の一つだからです」と、キンメルは部分的リプログラミングの可能性について述べています [78]。同時に、彼はカリコのリプログラミング研究は主に基礎的な疑問に答えるためのものであり、来年に治療法を展開するためのものではないと述べています [79]。「現時点では、これを臨床的に考えているわけではありません」と、現在のリプログラミング手法について語っています [80]。現在ニューリミットの共同創業者として、キンメルはAIとハイスループット実験を活用し、より安全なエピジェネティック・リプログラミング戦略の発見に取り組んでいます。2025年5月のインタビューで、ニューリミットはすでに3つのプロトタイプ分子を発見しており、これらは実験室でヒト肝細胞を若返らせ、老化した細胞の脂肪や毒素の処理能力をより若い状態に回復させることができると明かしました [81]。彼は、これらは初期の結果であり、ニューリミットがヒトでの治験を始めるまでには「数年かかる」と強調しました [82]。キンメルのバランスの取れた見解は、次のテーマを強調しています:可能性は非常に大きいが、実用化にはまだ初期段階である。
- Joan Mannick(Life Biosciences) – Life Bioの研究開発部門を率いるMannick博士は、部分的なエピジェネティック・リプログラミングを「潜在的に変革的」であり、加齢に伴う疾患の治療や予防に役立つ可能性があると述べています [83]。Life Biosciencesは、まず眼に焦点を当てたアプローチを取っています。Mannick博士は、眼は分裂する細胞が比較的少なく(がんリスクが低減)、閉じた器官であるため、有利な出発点だと説明しています [84]。OSK療法を眼の硝子体に注射すると、主にその場にとどまります。Life Bioの前臨床試験では、OSK遺伝子治療を眼に施したマウスで1.5年以上腫瘍が観察されていません [85]。「安全性が今私たちが最も重視していることです」とMannick博士は強調しました [86]。彼女も他の専門家同様、慎重かつ段階的な臨床アプローチ――一度に一つの組織を対象とすること――が、より広範な若返り治療への信頼とデータを築くと考えています。
要約すると、第一線の専門家たちは楽観的でありつつ慎重です。Altos LabsのCEO、Hal Barron博士が述べたように、共通の興奮があり、「加齢や疾患に関連する細胞機能障害は可逆的である可能性がある」とし、「生涯にわたって発生する疾患、けが、障害を逆転させることで患者の人生を変革できる可能性がある」と語っています [87]。同時に、多くの未知の点があることも認めています。コンセンサスとしては、メカニズム――どのエピジェネティック変化が最も重要で、どのように正確に標的化するか――を理解し、安全性を確保するために、より多くの研究が必要だということです。多くの専門家は、現在のエピジェネティック・リプログラミングの状況を1990年代の遺伝子治療に例えています――大きな可能性を秘めているが、正しく実現するには何年もの慎重な作業が必要だということです。
新たなプレイヤーたち:老化リセットを競う企業
これほど画期的な可能性があるため、エピジェネティック・リプログラミング分野には多額の資金と新興企業が殺到しているのも不思議ではありません。億万長者やバイオテクノロジー投資家は、単一の疾患治療にとどまらず、老化そのものに取り組む可能性を見出しています――もし成功すれば、革命的なことです。ここでは、主要な組織とその取り組みを紹介します。
- Altos Labs: おそらく最も注目を集めている新規参入企業であるAltos Labsは、2022年初頭に驚異的な30億ドルの資金調達で設立され、ジェフ・ベゾスやユーリ・ミルナーといった投資家に支えられています [88]。Altosはオールスター級の科学者チームを結成しており、山中伸弥、フアン・カルロス・イスピスア・ベルモンテ、ジェニファー・ダウドナなど多くの著名人が参加しています。同社の使命は、細胞若返りのディープバイオロジーを解明し、細胞を若返らせることで病気を逆転させる治療法を開発することです [89]。Altosは短期的な商業製品には注力せず、カリフォルニア、ケンブリッジ(英国)、日本に研究所を設立し、部分的なリプログラミングの基礎科学と、それがレジリエンスや再生に与える影響を追求しています [90]。設立のアイデアは、私たちが前述した科学から生まれました。山中氏は細胞の年齢を消去できることを示し、ベルモンテ氏は恩恵を得るために細胞のアイデンティティを消去する必要はないことを示しました [91]。Altosは、洗練されたOSKベースの介入法や新しい因子の組み合わせを研究している可能性が高いです。十分な資金を持つ民間の研究プロジェクトとして、同社は製品化のプレッシャーがかかる前に「良い科学」を提供するまでに5~10年の期間を見込んでいると表明しています [92]。Altosのリーダーたちは公の場で、目標は細胞を若返らせることで患者の病気を逆転させること、つまり影響を受けた細胞を再び若く健康にすることで病気を治療することだと述べています [93]。具体的なプロジェクトの多くはまだ非公開ですが、Altos Labsはこの分野の人材と知識の中心的なハブとなっていることは明らかです。
- Calico Life Sciences: 2013年にGoogle(Alphabet)によって、老化を理解するという野心的な目標のもと設立されたCalicoは、エピジェネティックなリプログラミングを含む老化メカニズムの研究を静かに進めてきました。Calicoの科学者(Jacob KimmelやCynthia Kenyonなど)は、短期間のOSKM活性化がヒト細胞にどのような影響を与えるかを探究しています [94]。2021年のCalicoのプレプリントでは、一時的な山中因子の発現でさえ、一部の細胞がアイデンティティを失い始める可能性があることが強調されており、慎重さの必要性が示されています [95]。Calicoのアプローチは主に探索的であり、「現時点では、これを臨床的に考えているわけではありません」とKimmelはリプログラミング研究について述べています [96]。その代わりに、Calicoはこのような研究を通じて細胞がどのように老化し、どのように若返るのかという根本的な疑問を探っています。Alphabetの潤沢な資金(および製薬会社AbbVieとの提携)により、Calicoは長期的な視点で取り組むことができます。他のアプローチ(長寿のための創薬スクリーニングなど)も調査している可能性がありますが、部分的リプログラミングは彼らが特に有望視している手法の一つです [97]。Calicoの姿勢は、応用における慎重さと科学への強い関心の両方を体現しています。
- Retro Biosciences: 2022年にステルスモードから登場したRetro Bioは、OpenAIで有名なサム・アルトマンが自身の資金1億8,000万ドルを投じて設立したことが明らかになり、大きな話題となりました [98]。Retroのミッションは大胆で、「人間の寿命を10年延ばす」ことを目指し、老化の細胞レベルの要因に働きかける介入法を開発しています [99]。同社は複数のアプローチを追求しており、特に細胞のリプログラミングとオートファジー(細胞のクリーニング機構)に注力しています [100]。RetroのCEOであるジョー・ベッツ=ラクロワは、最初の臨床試験(2025年頃開始予定)はオートファジー・プログラムから始まる可能性が高いと示唆しています。例えば、有害な細胞やタンパク質凝集体を除去する治療法などが、よりリスクの高いリプログラミング治療法が改良されるまでの足がかりとなるかもしれません [101]。しかし、Retroは部分的なリプログラミングの研究開発にも明らかに投資しており、AIの専門家(OpenAIとの契約も含む)と提携して、より優れた因子やデリバリーシステムの設計を進めています [102]。2023年までに、Retroはさらに10億ドルの資金調達を目指していると報じられており、その取り組みの本気度がうかがえます [103]。Retroの社風はスタートアップ的で野心的です。彼らの掲げる目標は、単一の疾患治療にとどまらず、「複数疾患の予防」を老化そのものに取り組むことで実現しようとしています [104]。チームやアドバイザーには長寿分野の著名人もおり、安全な候補が得られ次第、できるだけ早くヒトでの臨床試験に進む可能性が高いです。最初は特定の疾患(例えば高齢者の胸腺機能や肝機能の回復など―老化の特徴に基づく推測)での試験となるかもしれません。
- Life Biosciences: 2017年にDavid Sinclairによって共同設立されたLife Biosciencesは、加齢に関連する疾患の治療法としてエピジェネティック・リプログラミングに的を絞ってきました。Life Bioのアプローチは、高いインパクトと低リスクのバランスが取れた分野、つまり眼の疾患から始めることです。彼らはER-100という遺伝子治療法を開発しており、これはAAVウイルスベクターを用いてOSK(Oct4, Sox2, Klf4)を標的組織に直接送達します—特にc-Mycを除外しています— [105]。同社が報告した前臨床試験では、ER-100は動物モデルで顕著な効果を示しました:マウスの視神経損傷後の再生を改善し、緑内障モデルマウスの視力を回復させ、自然老化したマウスの視機能も向上させました [106]。前述の通り、Life Bioはサルの視神経梗塞(NAION)モデルでも視力回復を実証しました [107]—このブレークスルーは、彼らの治療法がヒトにも応用できる可能性を示しています。同社の短期的な目標は、このOSK遺伝子治療を急性緑内障またはNAIONに対する初の承認治療とすることであり、これは加齢関連の若返り治療の概念実証にもなります。Life BioのJoan Mannickは、眼は理想的な実証の場であると述べています。なぜなら、視力喪失は深刻な加齢関連障害であり、それを逆転できることを示すことは、細胞を「若返らせる」ことで機能を回復できる強力な例となるからです [108]。Life Biosciencesのより広いビジョンは、安全性が実証され次第、同じプラットフォームを他の組織にも応用することであり、部分的リプログラミングを通じて難聴や中枢神経系疾患などにも取り組む可能性があります(実際、Life Bioおよび関連会社は将来的に神経変性疾患への関心も示しています)。特筆すべきは、Life BioがIduna TherapeuticsというOSK治療に特化した部門を設立したことで、Sinclairも関与しており、緑内障プロジェクトにも取り組んできました [109]。
- Turn Biotechnologies:Turn Bioは、mRNA因子でヒト細胞の若返りに成功した科学者ヴィットリオ・セバスティアーノによって共同設立されたスタンフォード大学発のスピンオフ企業です。Turnは、ERA(Epigenetic Reprogramming of Aging)と呼ばれるmRNAベースのプラットフォームを開発し、リプログラミング因子を細胞内に一時的に導入しています [110]。修飾mRNA(COVIDワクチンに使われているものと類似)を用いて、OSKに加え追加因子(セバスティアーノの6因子カクテル:Oct4、Sox2、Klf4、Lin28、Nanog、さらに別のOct4バリアント)を細胞に導入できます [111]。mRNAは数日以内に分解されるため、リプログラミング因子の発現期間が自然に制限され、過剰な多能性化を回避する巧妙な方法となっています [112]。Turn Bioの最初のターゲットは皮膚の若返りで、主力候補TRN-001は、皮膚細胞の若々しい遺伝子発現を回復させることで加齢による皮膚や毛髪の改善を目指しています [113]。適応症には美容的な問題(しわ、脱毛)だけでなく、医療的な問題(創傷治癒不良、炎症性皮膚疾患)も含まれます [114]。皮膚はアクセスしやすいため、Turnは直接注射や外用で治療を試し、分子レベルの変化を確認するためのサンプルも回収できます。同社は前臨床試験で有望な結果を報告しており、皮膚の構造改善、細胞老化の減少、さらにはマウスでの白髪の再色素化まで観察され、mRNAアプローチが意図通りに機能していることを示唆しています [115]。Turnは皮膚科領域を超えて事業を拡大しており、製薬会社(HanAll)と3億ドルの提携を結び、眼および耳の疾患に対するリプログラミング技術を用いた治療法の開発を進めています [116]。これは、加齢黄斑変性や難聴などの疾患に対し、網膜細胞や蝸牛細胞をその場で若返らせることを目指している可能性を示唆します。TurnのmRNAデリバリーが安全であることが証明されれば、ウイルスやDNAを使わない方法で部分的なリプログラミングを実現でき、規制当局からもより好意的に受け止められる可能性があります。
- NewLimit: 2021年にCoinbaseのCEOブライアン・アームストロングらによって設立されたNewLimitは、エピジェネティック・リプログラミングによる人間の健康寿命の延長に明確に焦点を当てた資金力のあるスタートアップです [117]。2025年時点で1億3,000万ドル以上を調達しています [118]。NewLimitの戦略は最先端技術の融合です。シングルセルゲノミクスと機械学習を用いて、細胞がリプログラムされる際に何が変化するかを解析し、介入のターゲットを特定しています [119]。当初は特定の組織、特に免疫系、肝臓、血管系に集中し、これらを若返らせて加齢による衰えを治療することを目指しています [120]。最近のアップデートでは、NewLimitはプロトタイプ分子をいくつか発見し、これが肝細胞を部分的にリプログラムし、加齢した肝細胞の脂肪やアルコールの処理機能をより若い状態に回復させることができたと発表しました [121]。彼らのアプローチは、完全なOSKMを使わずに、細胞のエピゲノムをより若い状態に調整する小分子や遺伝子治療法を見つけることのようです。NewLimitはヒトでの臨床試験まで数年かかると認めています [122]が、加齢そのものを治療することで「どんな単一疾患よりも100倍大きな治療機会」に取り組んでいると位置付けています [123]。彼らはShift Bioscienceと同様、発見のスピードアップのために計算モデルに大きく依存しており、AIがリプログラミングの遺伝子ターゲットを提案し、ラボで検証し、そのデータでAIモデルを反復的に改良する「ラボ・イン・ア・ループ」実験を行っています [124]。NewLimitは、テクノロジー主導の新しいバイオテクノロジーの長寿分野における新しい波を象徴しています。
- その他: さらに多くの参入企業があります。Shift Bioscience(英国)は、約1,800万ドルの資金調達を受けており、AIによる「細胞シミュレーション」を用いて若返りのためのより安全な遺伝子の組み合わせを予測しています [125]。Rejuvenate Bio(ジョージ・チャーチが共同設立)は、加齢に関連する疾患の治療に遺伝子治療を用いていますが、焦点は必ずしもリプログラミングだけではありません(心臓病の犬への遺伝子治療から始めました)。AgeX Therapeutics(クローンや幹細胞の先駆者であるマイケル・ウェスト博士が率いる)は、部分的リプログラミング手法「誘導組織再生(iTR)」を提唱していますが、近年は進展が限定的です。YouthBio Therapeuticsは、2022年に報道されたスタートアップで、エピジェネティックな若返り(おそらく遺伝子治療による)を目指していますが、まだ初期段階です。さらに、Google Ventures(GV)や他のベンチャーキャピタルもこの分野に投資しています(NewLimitの共同創業者には元GVパートナーが含まれ、GVは以前セノリティクス分野のUnity Biotechも支援していました)。一方、大手製薬会社も注視したり提携したりしています。例えば、アッヴィはカリコと提携し、前述の通りHanAllはTurn Bioと提携しています。
すべての企業が全身を一度に全身的に若返らせることを計画しているわけではないことに注意が必要です――それは将来の壮大な目標です。ほとんどの企業は、まず加齢に伴う特定の疾患をターゲットにしています。例えば、OSK療法は最初に緑内障や加齢黄斑変性の治療、あるいは関節炎の関節の若返りや損傷した心臓の修復のための局所注射として承認されるかもしれません。アイデアは、まず1つの組織でコンセプトを証明し、その後拡大することです。しかし、これら多くの企業が共有する究極のビジョンは、実際に加齢を根本的なレベルで遅らせる、止める、あるいは逆転させることです。Retro Biosciencesが大胆に述べているように、彼らの目標は「複数疾患の予防」――本質的には加齢を根本原因として扱うことです [126]。部分的リプログラミングが安全に行えるようになれば、各社がさまざまな疾患に応用できるプラットフォームとなる可能性があります(例えば、遺伝子治療や抗体治療がプラットフォームとなったように)。Altosの30億ドル、Retroの1億8,000万ドル、NewLimitの資金など、資本の流入が急速な進展を後押ししています。これはわずか5年前、リプログラミングによる加齢逆転のアイデアがまだ初期段階で、主に学術研究室が細胞をいじっていた時代からの劇的な変化です。今や、本当の競争が始まっています。あるCEOが言ったように、「これは今や競争になった追求だ」 [127]――マウスから医療への部分的リプログラミングの応用を目指す競争です。
今後の応用例:健康寿命、疾患の逆転、再生
エピジェネティックな若返り技術が実現すれば、その応用は変革的なものとなるでしょう。科学者や企業が最も期待している可能性の一部を以下に挙げます。
- 寿命および健康寿命の延長: 最も広範な応用は、もちろん人間の老化そのものを遅らせたり逆転させたりすることです。つまり、人々がより長くそして健康的な人生を送れるということです。最良のシナリオでは、定期的な部分的リプログラミング治療によって体の細胞がより若い生物学的年齢にリセットされ、高齢期の多くの病気が発症するのを防ぐことができるかもしれません。動物データもこれをある程度支持しています。部分的リプログラミングを受けたマウスは、より長生きし、後年も健康を保ちました [128]。多くの人が強調するように、目標は単なる寿命ではなく、「健康寿命」—つまり、健康で過ごせる人生の割合です。「寿命を延ばすことが目的ではなく、私たちが重視しているのは健康寿命の延長です…長期間虚弱な状態で生きる必要がないようにすることです」とヴィットリオ・セバスティアーノは述べています [129]。実際的には、将来の高齢者は、体内の特定の幹細胞を部分的にリプログラムする遺伝子治療や薬剤を受け、臓器機能を若返らせ慢性疾患を防ぐことになるかもしれません。例えば、加齢による免疫機能の低下を改善するために血液幹細胞をリフレッシュする治療や、筋肉幹細胞を若返らせて虚弱や転倒を防ぐ治療などが考えられます。これらは推測の域を出ませんが、動物で実施されていることを考えれば突飛な話ではありません。とはいえ、リプログラミングによって実際に人間の寿命を延ばすには、何年にもわたる管理された臨床試験が必要です—これらの技術にとっては長期的な取り組みとなります。
- 加齢性疾患の治療: より差し迫った応用例としては、老化細胞が関与する特定の疾患に取り組み、それらの細胞を若い状態に若返らせることが挙げられます。すでに代表的な例が見られています:緑内障や視神経損傷による視力喪失です。網膜ニューロンをエピジェネティックにリセットすることで、研究者たちはマウスやサルの視力を回復させました [130]。これは本質的に、従来の薬剤を使うのではなく、細胞を再び若く回復力のある状態にすることで疾患(緑内障)を治療するものです。他の現実的な近い将来のターゲットには、神経変性疾患(アルツハイマー病やパーキンソン病など)が含まれます。ここでのアイデアは、特定の脳細胞やサポート細胞を若返らせて変性に抵抗させることです。実際、マウスの研究では、OSK療法が高齢マウスの記憶力や認知機能を改善する可能性が示唆されており、これはニューロンやグリア細胞の若返りによるものかもしれません(逸話的な結果が出てきていますが、まだ主要な学術誌には発表されていません)。心血管疾患も別のターゲットです:前述の通り、損傷したマウスの心臓に短期間のOSKMを投与すると再生が促進されました [131]。遺伝子治療によって、心筋梗塞後の心筋に部分的なリプログラミングを適用し、心臓の回復を助け、瘢痕組織を減らすことができるかもしれません。同様に、筋骨格系疾患—例えば変形性関節症や骨粗鬆症—では、軟骨や骨を維持する細胞を若返らせることで、関節や骨の健康を回復できる可能性があります。OcampoとBelmonteの研究者らは2016年に、部分的なリプログラミングによって高齢マウスの筋肉や膵臓細胞の再生が改善されることを示しました [132]。これは筋肉の萎縮や糖尿病の治療を示唆しています。肝疾患も、老化した肝細胞に若々しい機能を回復させるリプログラミング療法で対処できるかもしれません(興味深いことに、NewLimitの肝細胞に関する初期データでは、脂肪の移動が若い細胞のように再び行われることが示されています [133])。特定の腎疾患や慢性損傷でも、これらの臓器の老化細胞をより強靭で若々しい状態にリセットできれば、恩恵を受ける可能性があります。主な利点は、このアプローチが細胞レベルでホリスティックであることです:単一のタンパク質や経路を標的とするのではなく、リプログラミングによって数百もの加齢関連の変化を一度にリセットします [134]。したがって、疾患の複数の側面(例えば、細胞の代謝、分裂や組織修復能力、炎症シグナルの低減など)を同時に改善できる可能性があります。この幅広さこそが、科学者たちが部分的リプログラミングによって「加齢性疾患」というカテゴリー全体に取り組めるのではないかと夢見る理由です。
- 組織および臓器の再生: もう一つの注目すべき応用分野は、再生医療の領域です。現在、重度に損傷したり変性した臓器がある場合、幹細胞移植やラボで作られた臓器の置換を検討することがあります。しかし、部分的なリプログラミングは異なる解決策を提供します。すなわち、患者自身の細胞を若返らせることで、臓器を生体内で再生させるというものです。例えば、脊髄損傷や脳卒中後の患者を想像してみてください。部分的なリプログラミング療法によって、損傷部位周辺の神経細胞が活性化され、新たな成長や接続が促進され、回復を助けるかもしれません。高齢組織が再生できなくなる主な理由は、そこに存在する幹細胞が老化し休眠状態になるためであるという証拠もあります。リプログラミングによってそれらの細胞を再び活性化できる可能性があります。注目すべき例として、研究者たちは部分的なリプログラミングによって、老化した筋肉幹細胞の筋肉再生能力を高齢マウスで回復できることを発見しました [135]。したがって、筋肉幹細胞に定期的にOSKパルスを与えることで、筋肉の修復や構築を効率的に保つ、サルコペニア(加齢性筋肉減少症)の治療法が将来的に考えられます。創傷治癒の分野では、局所的なリプログラミングジェルが高齢患者の皮膚潰瘍の治癒を、創傷部位の皮膚細胞を若返らせることで助けるかもしれません。臓器特異的な応用も模索されています。例えば、胸腺(免疫細胞を作り、加齢とともに萎縮する臓器)に対して、部分的なリプログラミングで胸腺を若返らせ、70歳の免疫システムを若年の状態に戻せるかどうかを研究している科学者もいます。さらに、耳の有毛細胞(難聴のため)や眼の網膜細胞(視力のため)も再生できる可能性があり、Turn社やLife Bio社がそれぞれ [136]でターゲットとしています。基本的に、「老化した細胞が若い細胞のように治癒しない」あらゆる状態が候補となります。部分的なリプログラミングは、体外から細胞を置換するのではなく、体内で自分自身の細胞を若返らせるため、再生医療とアンチエイジング医療の境界を曖昧にします。その場で若返らせるのです。
- 早期老化疾患の治療: 最終的な目標は通常の老化の治療ですが、加速老化症(プロジェリア)のような稀な疾患にも効果が期待されています。2016年のBelmonteの研究は、実際にはプロジェリアマウスモデルで行われ、部分的なリプログラミングが明らかに健康と寿命を改善しました [137]。ヒトでは、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)という、子供に発症する致命的な加速老化疾患があります。部分的なエピジェネティックリプログラミングが、プロジェリア患者の細胞の老化を抑制できるかどうか、つまり彼らの寿命を延ばしたり症状を緩和したりできるかどうかに関心が集まっています。初期の細胞研究では、OSKがプロジェリアマウス由来の細胞を若返らせることが示されています [138]。もし遺伝子治療が安全に投与できれば、将来的には(プロジェリア患者は非常に脆弱であるため、十分な注意が必要ですが)この分野での試験が行われるかもしれません。
- 美容およびウェルネスでの利用: それほど重大ではない観点として、部分的なリプログラミングは美容用途にも使われる可能性があります。Turn Bioのような企業は、しわ、白髪、脱毛への対応を明確に掲げています [139]。皮膚細胞を若返らせることで、高齢者の皮膚の弾力性や厚み、見た目が改善されるかもしれません。毛包でのメラニン産生を回復させることで、白髪になった髪の色を取り戻すことができる可能性もあります(実際、マウスの実験では、OSK処理後に古い毛包から新しい黒髪が生えたことが示されています)。これらは命を救う治療法と比べると些細に思えるかもしれませんが、「若返り」市場は明らかに巨大です。重要なのは、これらが安全で本当に効果的であることを確保すること、そしてリスクのある領域に踏み込まないことです(誰も腫瘍のリスクがあるならOSKによるフェイスリフトは望みません)。しかし、これらの技術が医学的に洗練されれば、将来の「長寿クリニック」では健康と美容の両方のためにエピジェネティック・リプログラミング治療が提供されるかもしれません。
これらすべての応用がまだ開発中であることを強調することが重要です。2025年時点で、リプログラミングに基づく治療法は人間に対して承認されていません。最初の応用は、今後数年以内に臨床試験で行われる可能性が最も高いです(例えば、Life Biosciencesが眼の臨床試験を開始しようとしている、またはTurn Biotechが皮膚での試験を計画しているなど)。各ステップの成功――たとえばヒトの緑内障患者で視神経細胞を再生できれば――は、より広範な加齢性変性への挑戦に自信を与えるでしょう。
安全性、倫理、規制上の考慮事項
老化の逆転や細胞状態の大きな変化について語るときは常に、安全性リスクと倫理的な影響を考慮しなければなりません。部分的なリプログラミングは強力なツールであり、どんな強力なツールと同様に、潜在的な危険性を伴い、議論を呼び起こします。
がんリスク: 最も重要な安全性の懸念はがんです。山中因子はその性質上、細胞を胚性で急速に分裂する状態へと押し進めます。部分的な初期化であっても、ある程度の細胞増殖や状態変化が伴い、細胞が行き過ぎたり発がん性変異を獲得した場合、悪性腫瘍を引き起こす可能性があります。元々のOSKMカクテルに含まれるc-Mycは特に懸念されており、c-Mycはよく知られた癌遺伝子(がんを促進する遺伝子)です。これを軽減するため、現在では多くの研究がc-Mycを除外(OSKのみを使用)したり、細胞が誤った経路に進み始めた場合にすぐにシグナルをオフにできる誘導型システムを使用しています。これまでの動物実験では、短期間の周期的初期化で明らかながん形成は見られず、OSK(Mycなし)で数か月間処置したマウスも腫瘍がないと報告されています [140]。それでも、人間のような長寿命生物ではリスクを無視できません。治療した組織内のどの細胞も多能性化したり、制御不能に分裂し始めたりしないことを保証しなければなりません。ホッヘドリンガー博士が警告したように、「たった1つの細胞が…[iPSCになると]、その1つの細胞だけで腫瘍を作るのに十分です」 [141]。規制当局は動物での広範な発がん性バイオアッセイやヒト臨床試験での慎重なモニタリングを求めるでしょう。安全スイッチ(必要に応じて細胞を殺すことができる自殺遺伝子など)を遺伝子治療に組み込むことも検討されています。これは絶対に譲れないハードルです。若返りの恩恵は、がんリスクを大きく高めない場合にのみ価値があります。
ゲノム変異: 多くの初期化アプローチは遺伝子治療ベクター(AAVウイルスなど)を利用します。これらは通常ゲノムに組み込まれませんが、まれに組み込まれたり、複数挿入によって他の遺伝子が破壊される可能性もあります。また、オフターゲット効果の懸念もあります。部分的な初期化でトランスポゾン(ジャンピング遺伝子)が活性化されたり、ゲノムが微妙に不安定化したらどうなるでしょうか?長期的な動物実験で、部分的に初期化された細胞が安定性を保つのか、あるいは後になって奇妙な老化を示すのかを確認する必要があります。
アイデンティティと臓器機能の喪失: もう一つのリスクは、治療が行き過ぎて一部の細胞がアイデンティティを失ったり、正常に機能しなくなったりすることです。例えば、肝臓を部分的にリプログラムした場合、肝細胞の5%でも自分の本来の役割(血液の解毒など)をやめてしまうと、患者に害を及ぼす可能性があります。これは微妙なバランスです。若返りには古いエピジェネティックマークをある程度緩める必要がありますが、細胞が自分の役割を忘れてしまうほど緩めてはいけません。初期の研究では、適切なタイミングで因子を除去すれば、細胞は(組織特異的領域の「エピジェネティックメモリー」のおかげで)アイデンティティを再確立することが示唆されています [142]。しかし、細胞の種類によって反応が異なるかもしれません。例えばニューロンは非常に特殊で、分裂せず、非常に専門的な接続を持っています。これらを部分的にリプログラムすると、その接続を失ったり、神経伝達物質のプロファイルが変化したりするリスクがあります。マウスの視神経の実験では、継続的なOSK投与はニューロンに問題を引き起こしませんでした [143]。これは安心材料ですが、分裂しない細胞(ニューロンなど)の方が、頻繁に分裂する細胞(腸の上皮や皮膚など)よりも安全なターゲットかもしれません。後者は望ましくない変化が起こりやすい可能性があります。これは、ヒトで最初にどの組織を対象とするかに影響します。
免疫反応: ウイルスベクターや外来mRNAを使用する場合、体の免疫系が反応する可能性があります。AAVベクターは通常一度しか投与できません。なぜなら、体が抗体を作るからです。老化治療には繰り返しの治療サイクルが必要かもしれず、これは課題です。mRNAやタンパク質ベースのアプローチは、複数回投与できるためこの問題を回避できるかもしれませんが、投与システムによって強い免疫反応や炎症が引き起こされないよう注意が必要です。興味深いことに、一時的な炎症反応が若返りプロセスの一部である可能性もあり、いくつかの研究ではリプログラミング中に炎症関連遺伝子の発現変化が観察されています [144]。これは慎重なモニタリングが必要です。若返りを目指して自己免疫や慢性炎症を引き起こしてはなりません。
倫理的考慮: 倫理面では、主な疑問の一つは人間の寿命延長をどこまで追求すべきかということです。部分的リプログラミングによって人々が何十年も長く生きられるようになった場合、社会はおなじみの長寿倫理の問題に直面します。これらの治療を受けられるのは(最初はおそらく)裕福な人だけなのか?多くの人が120歳以上まで生きると、過密や資源の問題はどうなるのか?寿命延長治療の公平な分配をどう確保するのか?これらは科学を超えた広範な問題ですが、技術が成功すれば差し迫った課題となります。歴史的に見ても、抗生物質や臓器移植などの新しい医療の進歩は同様の問題を提起してきましたが、社会は適応してきました。しかし、長寿介入はその影響の規模において前例のないものとなる可能性があります。
もう一つの倫理的側面は、生殖細胞系列または胚の編集です。リプログラミングツールは、理論的には胚の段階で使用され、個人に長寿を「設計」することができるかもしれません(例えば、エピゲノムが非常に若々しく、回復力のある状態で始まるようにするなど)。しかし、ヒトの生殖細胞系列の遺伝子編集は、現在ほとんどの国で厳しく制限されているか、禁止されています。人間の胚を強化目的で編集すべきではないという合意があります。ヒト胚や生殖細胞系列でヤマナカ因子を使用することは、重大な倫理的問題を引き起こすだけでなく(実際、発生上の問題も引き起こす可能性が高いです)。したがって、焦点は体細胞治療—成人や子供の体内の細胞を治療し、将来の世代を変えることではありません。
規制の道筋: FDAのような規制当局は、これらの治療法がまず特定の疾患で試験されることを求めます。加齢自体は規制上の用語では疾患と認められていません(少なくとも現時点では)、そのため企業は加齢関連の疾患をターゲットにしなければなりません。例えば、治験は緑内障の治療や糖尿病患者の創傷治癒、サルコペニアにおける筋肉回復などが対象となるかもしれません。ある適応症で有効性と安全性が示されれば、より広い用途への道が開かれます。規制当局は長期的な結果を厳しく審査します:目的が長寿であるため、がんや他の問題の兆候について数年にわたる追跡調査が求められるかもしれません。2025年時点で、いくつかのエピジェネティック治療はすでに治験中です(リプログラミングではなく、DNAメチル化阻害剤や老化に対するテロメラーゼの遺伝子治療など)。これらは規制上の道をある程度切り開いています。しかし、部分的リプログラミングは十分に新しいため、さらなる慎重さが求められるかもしれません。最初のヒト試験は、問題が限定されるごく局所的な状態(例えば目や皮膚の一部)で行われ、その後、全身的な若返り(全身を「若返らせる」ための静脈内遺伝子治療など)が試みられるのは、かなり先の話になる可能性があります。
長寿に関する世論と倫理: 世論も重要です。一部の倫理学者は懸念を示しています:老化を逆転させることで「神の領域を侵す」ことになるのか?これによって社会的不平等が悪化するのではないか(もし若返りが富裕層だけのものになれば)?一方で、他の人々は、老化による苦しみを軽減することは道徳的義務であり、病気を治療するのと同じように扱うべきだと主張します。多くの主要な研究者は、健康寿命の延伸は、安全に行われ、できるだけ多くの人々に利益をもたらす限り、称賛すべき目標であるという立場を取っています。また、物語の枠組みも変化しています:「不老不死の探求」ではなく、アルツハイマー病、パーキンソン病、失明、心不全など、すべて加齢に関連する疾患を、老化そのものに取り組むことで予防するという話になっています。このような枠組みはより共感を呼びやすく、特定の疾患で改善が見られれば、世論の支持を得られる可能性があります。
結論
細胞の「年齢をリセットする」—老化した細胞を再び若返らせる—という概念は、かつてはSFの世界の話でした。今日では、実際にそれが可能であることを示す実験が行われており(少なくとも細胞や動物モデルで)、最先端の研究分野となっています。ヤマナカ因子(OSKM)を用いたエピジェネティックリプログラミングは、細胞を若返らせる最も有望な戦略の一つとして浮上しており、実質的に細胞の生物学的年齢を測るエピジェネティッククロックを巻き戻すことができます。リプログラミングプロセスを慎重に制御することで—部分的リプログラミングを通じて—科学者たちは、細胞、臓器、さらには動物全体で老化の兆候を逆転させることに成功しており、すべて細胞のアイデンティティや機能を失うことなく実現しています。
この意味するところは非常に深いものです。これは、老化が一方通行の不可避な劣化ではなく、ある程度までは可塑的で、さらには可逆的である可能性があるプロセスであることを示唆しています。ベルモンテ博士が言ったように、老化は「可塑的なプロセス」のようです――古い細胞は若さの記憶を保持しており、それが再活性化される可能性があるのです [145]。そして、シンクレア博士がマウスの若返りに成功した際に叫んだように、私たちはいつか「[老化を]自由自在に前進・後退させる」 [146]ことができるかもしれません。これらは、少し前までは懐疑的に受け止められていたであろう、非常に驚くべき主張です。しかし、増え続ける証拠は、治療的な年齢逆転の可能性を真剣に考えざるを得なくしています。
それでも、現実的な視点は必要です。実験室では細胞を若返らせることができ、マウスではいくつかの個体を治療して寿命を延ばすことができます。しかし、これを安全で効果的なヒト治療へと応用するのは、今や最も困難な部分です。今後数年で、部分的なリプログラミングに基づく治療法の最初の臨床試験が行われる可能性が高いでしょう――たとえば、視力喪失に対するOSK遺伝子治療や、皮膚の若返りのためのmRNA治療などです。これらの試験は、極めて重要な実証の場となります。もし、たとえ中程度の成功(たとえば、重大な副作用なしに組織機能が改善されるなど)が示されれば、この分野全体が正当化され、さらなる投資と研究が促進されるでしょう。
一方で、(安全性の問題や明確な効果が見られないなどの)試験の失敗は、過度な期待を抑えることになるかもしれません。生物学は複雑であることを忘れてはなりません。短命なマウスでうまくいったことが、長寿なヒトにそのまま当てはまるとは限らないのです。老化には多くの相互に関連したプロセスが関与しており、エピジェネティックな変化はその一部(とはいえ重要な部分)にすぎません。部分的なリプログラミングは、他の介入――たとえば老化細胞の除去や代謝の修復――と組み合わせる必要があるかもしれません。実際、一部の研究者はアプローチの組み合わせ(例:リプログラミングとラパマイシンのようなmTOR阻害剤の併用 [147])による相乗効果について議論しています。
今のところ、「エピゲノムのリセット」によって若さを取り戻すというアイデアは、科学界と一般の想像力を魅了しています。それは詩的な概念を含んでいます。つまり、私たち一人ひとりの中に、再び目覚めるのを待っている細胞の若いバージョンがまだ存在している、ということです。研究が進むにつれて、その可能性を引き出すことがどれほど現実的かが明らかになるでしょう。著名な科学者たちでさえ忍耐を勧めています——これは「短距離走ではなくマラソン」なのです [148]。しかし、これまでの進歩は驚くべきものでした。もしエピジェネティックな若返りアプローチが成功すれば、それは医学の新時代の幕開けとなるかもしれません。つまり、病気を治療するだけでなく、老化そのもののプロセスを本当に変えることで、人々がより長く健康でいられるようにするのです。今後10年で、山中の魔法の4遺伝子と、それに触発された技術が最終的に私たちの人生に命を加え——そしておそらく人生に年を加えることができるかどうかが明らかになるでしょう。
出典:
- ハーバード・メディカル・スクール・ニュース(2023年)– エピジェネティック情報の喪失が老化を引き起こし、回復がそれを逆転させる [149].
- サイエンティフィック・アメリカン(2022年)– 「億万長者が細胞若返り技術に資金提供…」 [150].
- サイエンスデイリー(2016年)– 細胞の初期化がマウスの老化を遅らせる [151].
- ネイチャー・コミュニケーションズ(2024年)– 初期化誘導による若返りの長く曲がりくねった道 [152].
- eLife(2022年)– Gillら、一過性初期化によるヒト細胞のマルチオミック若返り [153].
- Fierce Biotech(2023年)– Life Biosciencesの遺伝子治療が霊長類の視力を回復 [154].
- Altos Labs – サイエンス:部分的リプログラミングの基礎科学 [155].
- サイエンティフィック・アメリカン(2022年) – Kimmel、Mannickによる部分的リプログラミングに関する引用 [156] .
- TechCrunch(2025年) – NewLimitが1億3,000万ドルを調達…エピジェネティック・リプログラミングの進展 [157].
- Labiotech.eu(2025年) – アンチエイジング・バイオテク企業(Retro、Turnなど) [158].
- Life Biosciences(2025年) – 私たちのサイエンス:視力のためのOSK遺伝子治療 [159].
- Nature Cell(2016年) – Ocampoら、部分的リプログラミングによる加齢関連の特徴のin vivo改善 [160]、および関連する解説 [161].
References
1. www.scientificamerican.com, 2. www.sciencedaily.com, 3. www.nature.com, 4. hms.harvard.edu, 5. www.lifebiosciences.com, 6. www.lifebiosciences.com, 7. www.sciencedaily.com, 8. www.nature.com, 9. hms.harvard.edu, 10. www.scientificamerican.com, 11. www.altoslabs.com, 12. www.altoslabs.com, 13. www.scientificamerican.com, 14. www.sciencedaily.com, 15. elifesciences.org, 16. www.scientificamerican.com, 17. www.scientificamerican.com, 18. www.scientificamerican.com, 19. www.scientificamerican.com, 20. www.sciencedaily.com, 21. www.sciencedaily.com, 22. www.sciencedaily.com, 23. www.sciencedaily.com, 24. www.sciencedaily.com, 25. www.sciencedaily.com, 26. www.scientificamerican.com, 27. www.scientificamerican.com, 28. www.scientificamerican.com, 29. www.nature.com, 30. www.nature.com, 31. www.nature.com, 32. www.nature.com, 33. www.nature.com, 34. www.nature.com, 35. www.nature.com, 36. www.nature.com, 37. www.nature.com, 38. www.nature.com, 39. www.nature.com, 40. www.nature.com, 41. www.nature.com, 42. www.nature.com, 43. hms.harvard.edu, 44. hms.harvard.edu, 45. hms.harvard.edu, 46. hms.harvard.edu, 47. hms.harvard.edu, 48. elifesciences.org, 49. elifesciences.org, 50. elifesciences.org, 51. elifesciences.org, 52. elifesciences.org, 53. www.nature.com, 54. www.nature.com, 55. www.nature.com, 56. www.nature.com, 57. www.fiercebiotech.com, 58. www.fiercebiotech.com, 59. www.fiercebiotech.com, 60. www.fiercebiotech.com, 61. www.lifebiosciences.com, 62. www.lifebiosciences.com, 63. www.nature.com, 64. www.nature.com, 65. www.nature.com, 66. hms.harvard.edu, 67. www.scientificamerican.com, 68. hms.harvard.edu, 69. hms.harvard.edu, 70. hms.harvard.edu, 71. www.sciencedaily.com, 72. www.sciencedaily.com, 73. www.altoslabs.com, 74. www.scientificamerican.com, 75. www.scientificamerican.com, 76. www.scientificamerican.com, 77. www.scientificamerican.com, 78. www.scientificamerican.com, 79. www.scientificamerican.com, 80. www.scientificamerican.com, 81. techcrunch.com, 82. techcrunch.com, 83. www.scientificamerican.com, 84. www.scientificamerican.com, 85. www.scientificamerican.com, 86. www.scientificamerican.com, 87. www.altoslabs.com, 88. www.scientificamerican.com, 89. www.altoslabs.com, 90. www.scientificamerican.com, 91. www.altoslabs.com, 92. www.scientificamerican.com, 93. www.altoslabs.com, 94. www.scientificamerican.com, 95. www.scientificamerican.com, 96. www.scientificamerican.com, 97. www.scientificamerican.com, 98. www.labiotech.eu, 99. www.labiotech.eu, 100. www.labiotech.eu, 101. www.labiotech.eu, 102. www.labiotech.eu, 103. techcrunch.com, 104. www.labiotech.eu, 105. www.lifebiosciences.com, 106. www.lifebiosciences.com, 107. www.fiercebiotech.com, 108. www.fiercebiotech.com, 109. www.lifespan.io, 110. www.labiotech.eu, 111. www.scientificamerican.com, 112. www.scientificamerican.com, 113. www.labiotech.eu, 114. www.labiotech.eu, 115. www.labiotech.eu, 116. www.labiotech.eu, 117. www.newlimit.com, 118. techcrunch.com, 119. www.newlimit.com, 120. www.newlimit.com, 121. techcrunch.com, 122. techcrunch.com, 123. firstwordpharma.com, 124. techcrunch.com, 125. www.labiotech.eu, 126. www.labiotech.eu, 127. www.scientificamerican.com, 128. www.nature.com, 129. www.scientificamerican.com, 130. www.fiercebiotech.com, 131. www.nature.com, 132. www.sciencedaily.com, 133. techcrunch.com, 134. elifesciences.org, 135. www.nature.com, 136. www.labiotech.eu, 137. www.sciencedaily.com, 138. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 139. www.labiotech.eu, 140. www.scientificamerican.com, 141. www.scientificamerican.com, 142. elifesciences.org, 143. www.nature.com, 144. www.lifespan.io, 145. www.sciencedaily.com, 146. hms.harvard.edu, 147. pmc.ncbi.nlm.nih.gov, 148. www.scientificamerican.com, 149. hms.harvard.edu, 150. www.scientificamerican.com, 151. www.sciencedaily.com, 152. www.nature.com, 153. elifesciences.org, 154. www.fiercebiotech.com, 155. www.altoslabs.com, 156. www.scientificamerican.com, 157. techcrunch.com, 158. www.labiotech.eu, 159. www.lifebiosciences.com, 160. www.sciencedaily.com, 161. www.sciencedaily.com